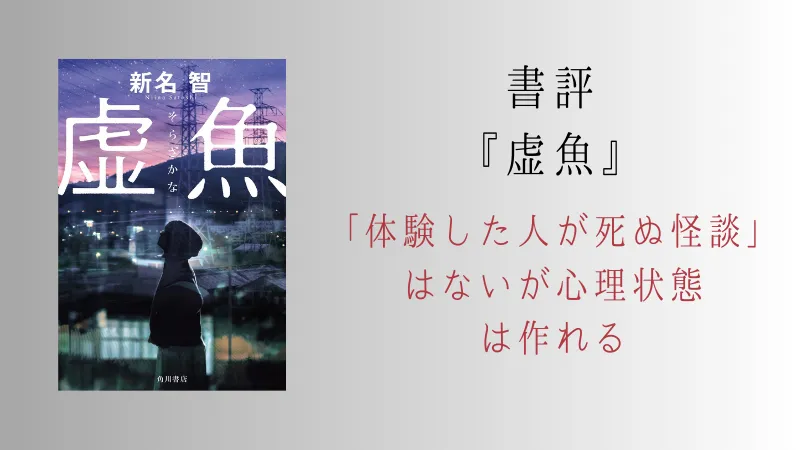【注意】この記事は小説『虚魚(そらざかな)』のネタバレを含みます。
3つの点が逆三角形に並んでいると、それが人間や動物の顔に見えることがあります。
このような現象を心理学で「パレイドリア」と呼びます。
雲や岩肌、樹木の模様が顔に見えるのも、パレイドリアです。
なぜ、人間の脳にこのような性質が備わっているのかは諸説あります。
その中でも有力な説は「生存のため」という進化的な理由です。
例えば、ジャングルに迷い込んだとき、樹木の模様を「顔だ!」と勘違いするのは、それほど危険なことではありません。
しかし、木々の間に隠れて獲物を狙っている人喰い族の顔を「顔ではないもの」と勘違いするのは、敵に気づくのが遅れるということですから、生存の危機です。
そのため、人間の脳は「顔っぽいもの」に対し、過敏に反応する能力が高くなったということです。
幽霊を信じるのもパレイドリア
人間が幽霊や妖怪の存在を信じるのも、パレイドリアで説明することが可能です。
これ自体は必ずしも悪いことではありません。慰めにつながることさえあります。
例えば、幼い娘を失った母親が、「幽霊でも良いから娘に再会したい」と思っていたとします。
このような願望を持っていれば、踏切を通る電車の車両の隙間の奥で揺れた木の葉が、娘の顔に見えたり、風で木々が揺れる音が娘の声に聞こえることもあるでしょう。
それらをポジティブなメッセージと感じることができれば、生前の娘は幸せだったとか、天国から自分を見ていると思えます。それによって、精神的な安定を保つことができます。
パレイドリアが怪談話に変化するまで
こうした体験が、怪談話の萌芽となっていることも、あるかもしれません。
例えば、パレイドリアによって娘の姿を見た母親が、誰かに「あそこの踏切に娘が見えたの」と言ったとします。
それを聞いた人が、また別の誰かにその話をします。それが伝わっていくうちに、どこかのタイミングで、その踏切の近くで事故が起こったとしたら、「少女の怨念だ」などと言いだす人が出てくるのです。
それが怪談話として拡散する中、今度は息子を失った別の母親まで届いたとします。
この母親には「子供の霊が出る」と伝わったとします。子供の性別は確定されていません。
しかし、この母親の「息子に会いたい」という気持ちが強かったら、誰かに伝えるとき、無意識に「男の子の霊が」と言うこともあるのです。
明確に「自分の息子の霊である」と言うこともあるかもしれません。
つまり、怪談というのは元はパレイドリアによる勘違いだったものが、それを体験した人や、話す人の情念を吸い込みながら、口承されることで完成されるものかもしれないのです。
『虚魚』(著:新名智)という小説
ほとんどの怪談というのは、こうした流れによって生まれてきたのではないかと思わせてくれるのが、『虚魚』(著:新名智)という小説です。
2021年の『第41回横溝正史ミステリ&ホラー大賞』にも選ばれた作品です。
この作品には“体験した人が死ぬ怪談”を探している怪談師の三咲と、“呪いか祟りで死にたい”と思っている居候のカナちゃんという、2人の登場人物が出てきます。
ある日、カナちゃんが「釣り上げた人が死んでしまう魚」がいるらしい、という怪談を仕入れてきます。
その真相を確かめるべく2人は、現地へと向かいます。調査を進める中で、場所によってこの怪談の内容が変化していることに気がつきます。
そして自分達も、その怪談に絡めとられていくのです。
なぜなら、三咲とカナちゃんも、怪談に染み込ませるべき情念を持っているからです。
「体験した人が死ぬ怪談」はあるのか?
三咲は観客に怖い話を聞かせる「怪談師」でありながら、心霊や呪術を信じてはいません。しかし、仮にそういったものが存在するなら知りたいと思っています。
なぜなら、葬り去りたいほどに憎い相手がいるからです。
これに対し、カナちゃんは、過去の体験から、呪いや祟りが本当に存在するのではないかと思っています。
しかし、信じたくないと思っています。なぜなら呪いや祟りが存在しないと分かれば、過去の体験による罪悪感から逃れることができるからです。
このように心霊現象を信じているかどうかによっても、同じ現象に遭遇したときの、受け止め方は変わります。
逆三角形の3つの点を見たとき、一方はただの点と受け止め、一方は人間と受け止めるパレイドリアが起こるのです。
そしてこの現象は、第三者によって悪用されることもあります。
特に罪悪感や悲しみなどのネガティブな感情を持っているとき、人間は冷静な判断力を失いますから、簡単に騙されてしまうのです。
「死んだアイツの霊が復讐にやってきた」と言われたら、些細な物音でも、そう思わされてしまうのです。
そして、「〇〇をすれば助かる」と言われたら、信じて実行してしまうでしょう。それによって自分の命を落とすこともあるかもしれません。
この作品の主人公である三咲は、「体験した人が死ぬ怪談」を探し求めていました。それが実在するかは不明ですが、怪談を使って誰かをそういう気持ちにさせるのは、不可能ではないということです。
自分を守るはずの機能が自分を傷つける皮肉
パレイドリアという現象は本来、自分を守るために進化した機能のはずです。
しかし、それが時に幽霊の存在を信じさせ、破滅的な行動へと駆り立てる原因となるのは皮肉です。
たとえ信じていなくとも、精神的に弱っているときであれば、騙されてしまうこともあるでしょう。
今回の『虚魚』は、曖昧に作られた怪談話にさえ、騙され自分を傷つけてしまうほどに、人間は不安定な動物であるということを、テンポよく描いた作品でした。