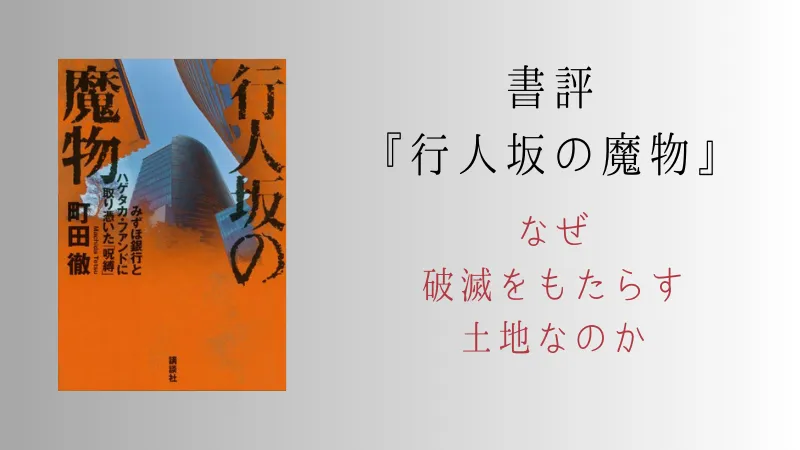目黒区の下目黒1丁目に行人坂(ぎょうにんざか)という坂があります。
行者(仏道などの修行をする人)が寺を建てたことから、この名前がついたといわれています。
土地勘のある人なら、ホテル雅叙園東京の北側の急な坂といえば、行人坂の位置が分かるでしょう。そこにある大円寺こそが、行者の建てた寺です。
この寺や雅叙園を含め、このあたり一帯には大昔から、怨念めいた事件がいくつも起こってきました。そして多くの者たちに破滅をもたらしました。
似た名前の別のホテルが2つ
かつて行人坂の南側の土地には「雅叙園観光ホテル」がありました。紛らわしいのですが、現在もホテルや結婚式場を運営している「ホテル雅叙園東京」とは別の物です。
元をただせば両社は無関係ではありませんが、現在の「ホテル雅叙園東京」からしたら、無関係と言いたいのではないでしょうか。「勝手に同じような名前をつけられただけ」だと。
どういうことかというと、現在の「ホテル雅叙園東京」がまだ、それほど大規模に宿泊業を展開していなかったときに、ビルの一部をテナントとして貸し出したところ、それを借りた松尾國三という人物が「雅叙園観光ホテル」という名前でホテルを開業してしまったのです。
なぜ紛らわしい名称を使用しても訴えられなかったかというと、本元である「ホテル雅叙園東京(当時の名称は雅叙園)」の権利の何割かを持つ、創業家の人間を取締役に入れたからです。
本元の雅叙園では創業者が亡くなった直後で、後継者を争って親族間で対立が起こっていたため、松尾はそこに目をつけたのです。
やがて、この松尾が亡くなると今度は、パクッた側の雅叙園観光ホテルでも、後継者争いが起こります。そこに入り込んだのが、コスモポリタンという会社の経営者である池田保次です。しかし、池田は資金繰りに窮すると、雅叙園観光ホテルの手形を乱発し、やがて失踪します。
戦後最大の経済事件『イトマン事件』の発端
失踪した池田の雅叙園観光ホテルに多額の金を貸していたのが、実業家の許永中(きょえいちゅう)や伊藤寿永光(いとうすえみつ)です。
ある年齢以上の人ならこの2人の名前でピンとくるでしょうが、戦後最大の経済事件といわれた「イトマン事件」の主役たちです。
実は、この雅叙園観光ホテルにおける一連の出来事こそが、イトマン事件の発端なのです。
雅叙園観光が潰れてしまうと許永中や伊藤寿永光は、貸した金が返ってこなくなります。そこで商社のイトマンに雅叙園観光を救済させるための出資をさせたのです。
そこから、イトマンはその他の案件でも、打出の小槌のように使われ、数千億円が裏社会に流れたといわれています。
『行人坂の魔物』
こういった複雑な事情について書かれているのが『行人坂の魔物』(著:町田徹)です。
この本には、江戸時代から現代までに、行人坂で起こった様々な事件が、当時の時代背景や経済情勢を交えながら詳しく書かれています。
この地における事件といえば、ここまで説明した雅叙園観光ホテルの一連の騒動が有名ですが、実はそれ以外にも、江戸時代の「明和の大火」と呼ばれる火事や、2000年代に入ってからのハゲタカファンドによる不良債権買い叩きによる乗っ取りなど、陰謀渦巻く事件が起こっているのです。
サブタイトルの「みずほ銀行とハゲタカ・ファンドに取り憑いた呪縛」だけを見ると、外資系ファンドと日本の事業会社のバトルを描いたノンフィクションをイメージするかもしれません。
もちろん、そこにも触れてはいますが、それ以外の事件にも多くの紙面を割いています。前半部分は、江戸時代からの「歴史」の説明といっても良いくらいです。なので他の経済ノンフィクションと同じような内容を期待して読むと、歴史の説明が長すぎると感じるかもしれません。
「魔物」とは何か
『行人坂の魔物』では、この地で金儲けをしようとした人間に破滅をもたらす見えない力を「魔物」と表現しています。
ではこの「魔物」の正体は何なのでしょうか?
それに対する明確な答えは書かれてはいませんし、何かをすると必ず失敗するようないわくつきの土地などというものが存在するかも分かりません。
行人坂は過信をもたらす
個人的な話をさせてもらうと、私自身は都市伝説や怪談は好きですが、心霊やカルトといった科学的根拠のないものは、信じないほうです。
しかし、実際にどんな商売をやってもうまく行かなかったり、事故が起こりやすい場所というのは存在するものです。どこの地域にも頻繁にテナントが入れ替わっている建物があったりします。
こういった場所は「何となく入りたくない」という心理にさせてしまうのです。その原因は道路との接し方や、日の当たり方、眺望など様々ですが、そういったものが無意識に影響を与えているのです。
では行人坂の一帯は、人をどのような心理状態にさせるのでしょうか?
もしかすると「過信」をもたらすのかもしれません。
人間は高い所にのぼると過信する
マイアミ大学の研究者らが、3,000社以上のヘッジファンドの入居階数を調べた研究があります。それによると、ビルの高層階に入っているヘッジファンドほど、リスクの高い投資をしている傾向にあったのです。(※1)
なぜこのようなことになるかというと、人間というのは高いところにいると、自分に力があるような感覚を持ちやすいからです。これも心理学の研究によって証明されています。
行人坂の一帯は、丘や坂、崖といった否が応でも、高低差を感じさせる形状です。
多くの先人たちが破滅する姿を見たとしても、その高みにのぼると「自分だけはうまくやれる」という過信が芽生えてしまうのではないでしょうか?
その結果、取る必要のないリスクを取ったり、時代を読み違えたりして、失敗してしまうのかもしれません。
最近の経済事件の被告人のオフィスや自宅を見ても、高い所にあるケースが多い気はしないでしょうか?
※1 参考文献:Sina Esteky, Jean D. Wineman, David B. Wooten. (2017). The Influence of Physical Elevation in Buildings on Risk Preferences: Evidence from a Pilot and Four Field Studies.